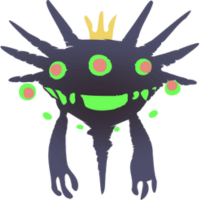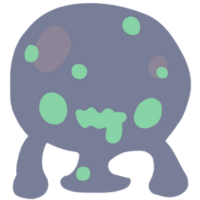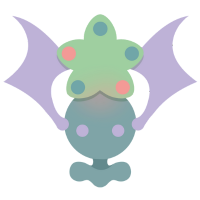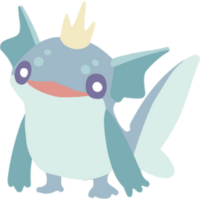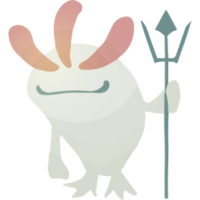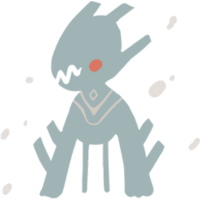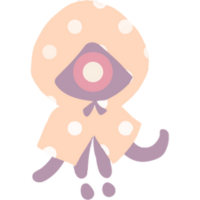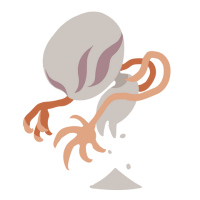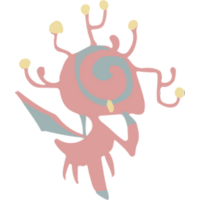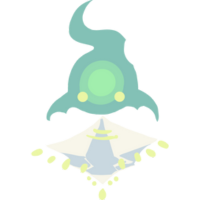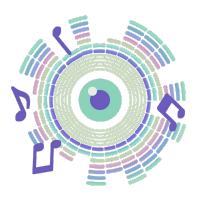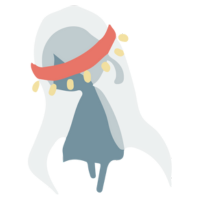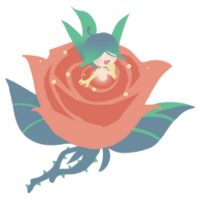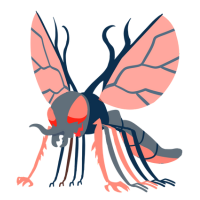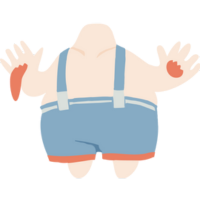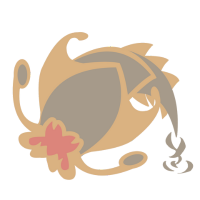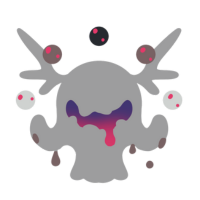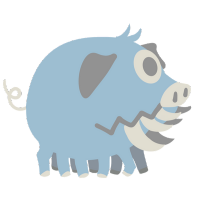【2025年版】「アウトサイダー」入門|あらすじ・登場人物:おすすめ版まとめ
The Outsider
概要
本作は2,620語の短編小説で、1921年の春か夏頃に執筆されたと推測される。初出はWeird Tales誌1926年4月号で、同誌1931年6・7月合併号に再掲された。単行本初収録はO、校訂版はDH、詳註版はCCに収録されている。
『アウトサイダー』は、その構造において夢のような非論理性を持つ物語である。主人公の経験や発見は、「彼が遠い過去に、人間の先祖である可能性を示唆する」が、その長寿や蘇生の理由は説明されていない。また、物語の舞台が現実なのか想像の産物なのかも曖昧である。
物語の結末、特に主人公が鏡で自身の姿を見る場面は、多くの文学作品との類似性が指摘されている。エドガー・アラン・ポーの『ウィリアム・ウィルスン』、オスカー・ワイルドの『王女の誕生日』、ナサニエル・ホーソーンの『ある孤独な男の日記より』、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』などが挙げられる。
しかし、最も説得力のある見方は、この作品がポーへのオマージュだというものである。ラヴクラフト自身も、この作品を「ポーの文字通りの、さりながら無意識の模倣が最高潮に達したもの」と評している。特に導入部は『ベレニス』を、城の描写は『赤き死の仮面』を想起させる。
ラヴクラフトは後年、この作品が複数のクライマックスを持つ構造で構成されたことを明かしている。墓地のエピソード、人々の反応、そして最後の自己認識という三段階の展開が意図的に組み立てられたという。
作品の自伝的要素については議論が分かれる。主人公の孤独感や疎外感は、ラヴクラフトの人生を反映しているという見方もあるが、少年時代の描写など、作者の実際の経験とは矛盾する部分もある。しかし、大局的には、ラヴクラフトの自己認識や内面の葛藤を反映した作品だと解釈することができるだろう。
登場人物
- 語り手
舞台
- ネフレン=カの地下墓地
あらすじ
鏡のない古城に住まう正体不明の語り手。半生を孤独に過ごし、老人の世話を受けながら生きてきた彼の心に、ある日、変化が訪れる。閉ざされた世界から脱し、光を求める強い衝動に駆られたのだ。
決意を胸に、城内で最も高い塔へと挑む。困難な登攀の末、塔頂にたどり着いた彼を待っていたのは、想像を超える歓喜の光景。鉄格子越しに見える石段、そして記憶にすらない満月の輝き。しかし、その喜びもつかの間、恐ろしい事実に気づく。彼がいるのは高所ではなく、ただの地上だったのだ。
この衝撃的な発見に茫然自失となった語り手は、さまよい歩くうちに別の城へと辿り着く。蔦に覆われ、荒れ果てたその城は、不思議にも懐かしさと違和感が入り混じる場所だった。
城内から聞こえる陽気な人々の声に誘われ、窓から中へ入ろうとする語り手。しかし、そこで彼を待ち受けていたのは、予想もしない衝撃的な光景だった。
果たして語り手の見た世界は現実なのか、それとも幻想なのか。
邦訳版の比較ガイド おすすめの一冊はどれ?
現在入手可能な主要な邦訳版として、以下の収録版がある:
- 「ラヴクラフト全集3」:ラヴクラフトの「履歴書」が合わせて読める。

初読者には「ラヴクラフト全集3」がおすすめっ。現在、邦訳版はこの書籍にのみ収録されています。
購入ガイド&リンク集
「ラヴクラフト全集3」:紙版/電子版
- amazon(Kindle版:有):「ラヴクラフト全集 3 | H・P・ラヴクラフト, 大瀧 啓裕 | 英米の小説・文芸 | Kindleストア | Amazon」
- ebookjapan:「ラヴクラフト全集 (3) (創元推理文庫) – 著:H・P・ラヴクラフト 訳:大瀧啓裕 – 無料漫画・試し読み!電子書籍通販 ebookjapan」