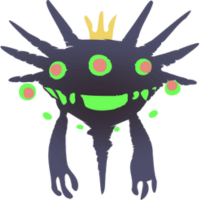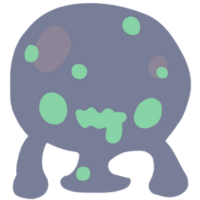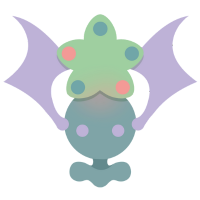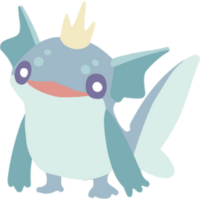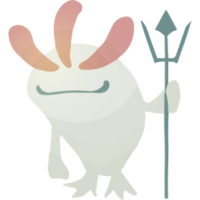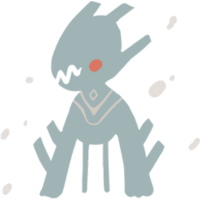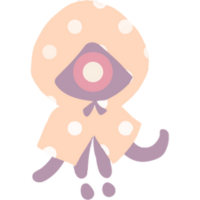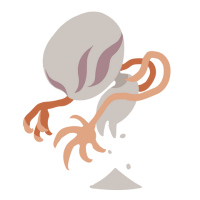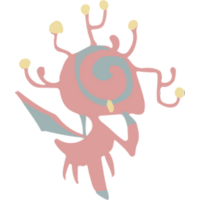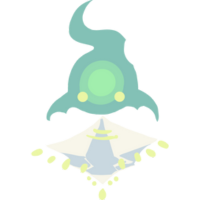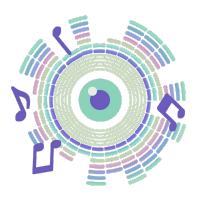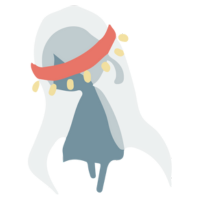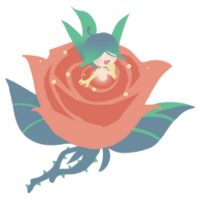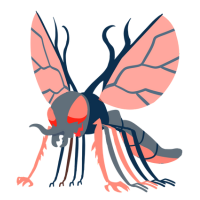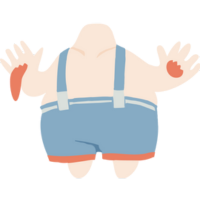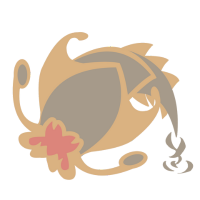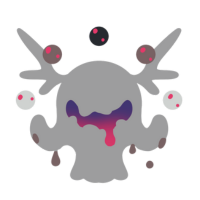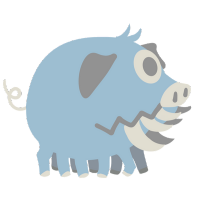クトゥルーの呼び声
The Call of Cthulhu
概要
【概要】
本作は12,000語の短編小説で、1926年の8月か9月に執筆されている。初出は1928年、『Weird Tales』の2月号で、後に『The Outsider and Others』に収録された。校訂版が『The Dunwich Horror and Others』に、詳註版が『More Annotated H.P.Lovecraft』と『The Call of Cthulhu and Other Weird Stories』に収録されている。
2月号モーパッサンの『オルラ』とマッケンの『黒い石印』からの文学的影響を受けている。前者はフランスに到来した不可視の存在に焦点を当て、後者は情報をまとめ上げて信念を醸成する要素が類似している。特に、「イクサクサル」の名前や六十石は「クトゥルー」を連想させる。
他にも物語中にW・スコット=エリオットの『The Story of Atlantis and the Lost Lemuria』の引用があり、神智学に関する話題が登場する。また、A・メリットの『ムーン・プール』も影響を与えており、特に地底世界への扉の開放とクトゥルーの解放に類似した要素が存在する。
物語にはいくつかの自伝的な要素が含まれており、登場人物の名前や場所にはラヴクラフトの実際の経験や関連性が見られる。たとえば、語り手の名前であるサーストンはブラウン大学の学長であったフランシス・ウェイランドからインスパイアされており、ギャマルやエインジェルといった名前もラブクラフトの環境や家族と関連している。ウィルコックスの名前はラヴクラフトの先祖に由来し、評論家のジェイムズ・F・モートンと思われる人物についての言及もある。さらに作中で言及された地震は実際に発生した出来事である。
ラヴクラフトは「クトゥルー」の発音に関して異なる見解を示しており、その中で最も詳細な説明は1934年の手紙にあり、「「クトゥルー」の発音は、人間の器官では模倣できない地獄めいた存在の言葉を表現するものであり、具体的な音節は不明瞭な喉音を含むものである」と述べている。しいて人の言葉で書き起こすなら「Khlu^l’-hloo」が近いとされ、最初の音節は「klutz」に似ているかもしれないと説明している。ただし、ラヴクラフト自身の発音を聞いた友人たちの記録にはばらつきがあり、一般的に広まった「Kathoo-loo」は正確ではないことが指摘されている。
【収録】
- 「クトゥルー1」
- 「新訳クトゥルー神話コレクション1」
- 「ラヴクラフト全集2」
登場人物
【登場人物】
- フランシス・ウェイランド・サーストン
- ジョージ・ギャメル・エンジェル…大叔父
- ヘンリ・アンソニー・ウィルコックス…彫刻家
- トビー医師…ウィルコックスの担当医
- ジョン・レイモンド・ルグラース警視正…クトゥルフ教団の儀式を見た人
- ウィリアム・チャニング・ウェッブ…教授、探検家、グリーンランドあたりでクトゥルーの彫像を見た人
- ジョゼフ・D・ガルベス…ルグラースの部下…儀式の時に白い何かを見た人
- カストロ…クトゥルー教団の信徒
- グスタフ・ヨハンセン
- ウィリアム・ブライデン
【舞台】
- 1925〜27年 アメリカ
あらすじ
【あらすじ】
主人公のフランシス・ウェイランド・サーストンは、亡くなった大叔父エインジェルの部屋を片付けている最中、想像を絶する発見をする。ブラウン大学でセム語教授を務めていたエインジェルが生涯をかけて集めた、異様なデータの数々。その中で特に目を引いたのは、彫刻家ウィルコックスの不可解な作品と、彼の見た夢の記録だった。そこに繰り返し現れる「クトゥルー・フタグン」という言葉。その意味は不明だが、何か重要な鍵を握っているように思えた。
物語は更なる謎へと発展していく。ある日の会合で、警視正ルグラースが同様の奇妙な彫刻を持ち込んだのだ。彼の証言によると、ルイジアナの沼地でカルト教団の儀式を目撃したという。そこで信者たちが唱えていた呪文のような言葉—「ふんぐるい むぐるうなふ くとぅるー るるいえ うがふなぐる ふたぐん」。
この時エインジェルも見逃していたは重大な事実が発覚する。教団が儀式を行った同日、一隻の船が帰還していたのだ。
語り手は次第に、人知を超えた何かの存在を確信していく。しかし、その真実に近づけば近づくほど、彼を取り巻く世界の常識が崩れ去っていく。果たして人類は、この途方もない真実を受け入れることができるのだろうか。そして、クトゥルーとは一体何なのか。