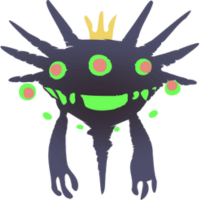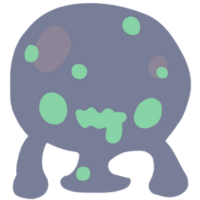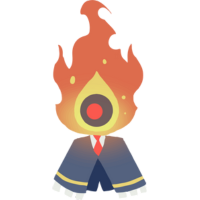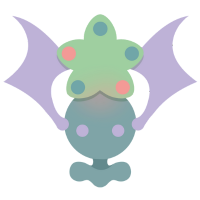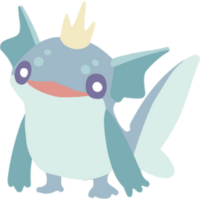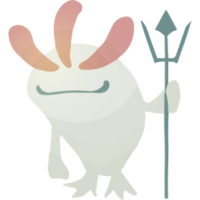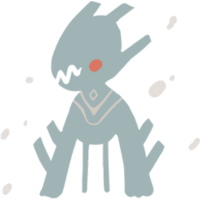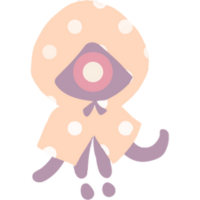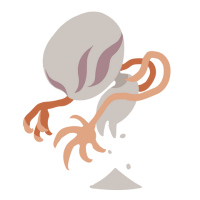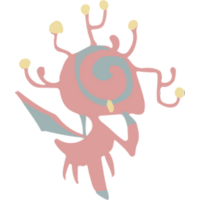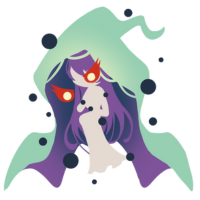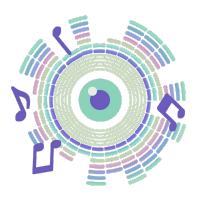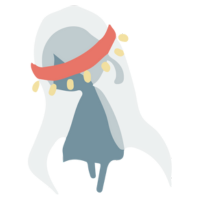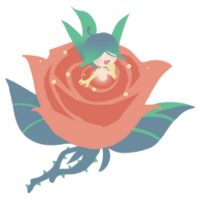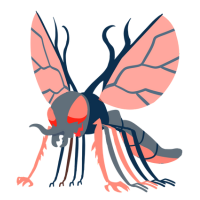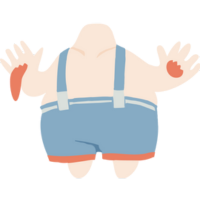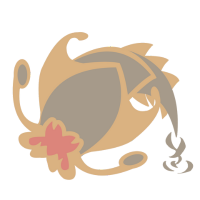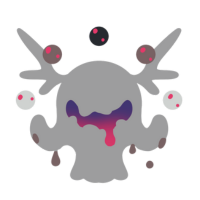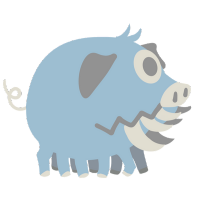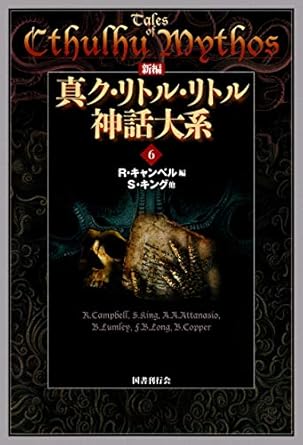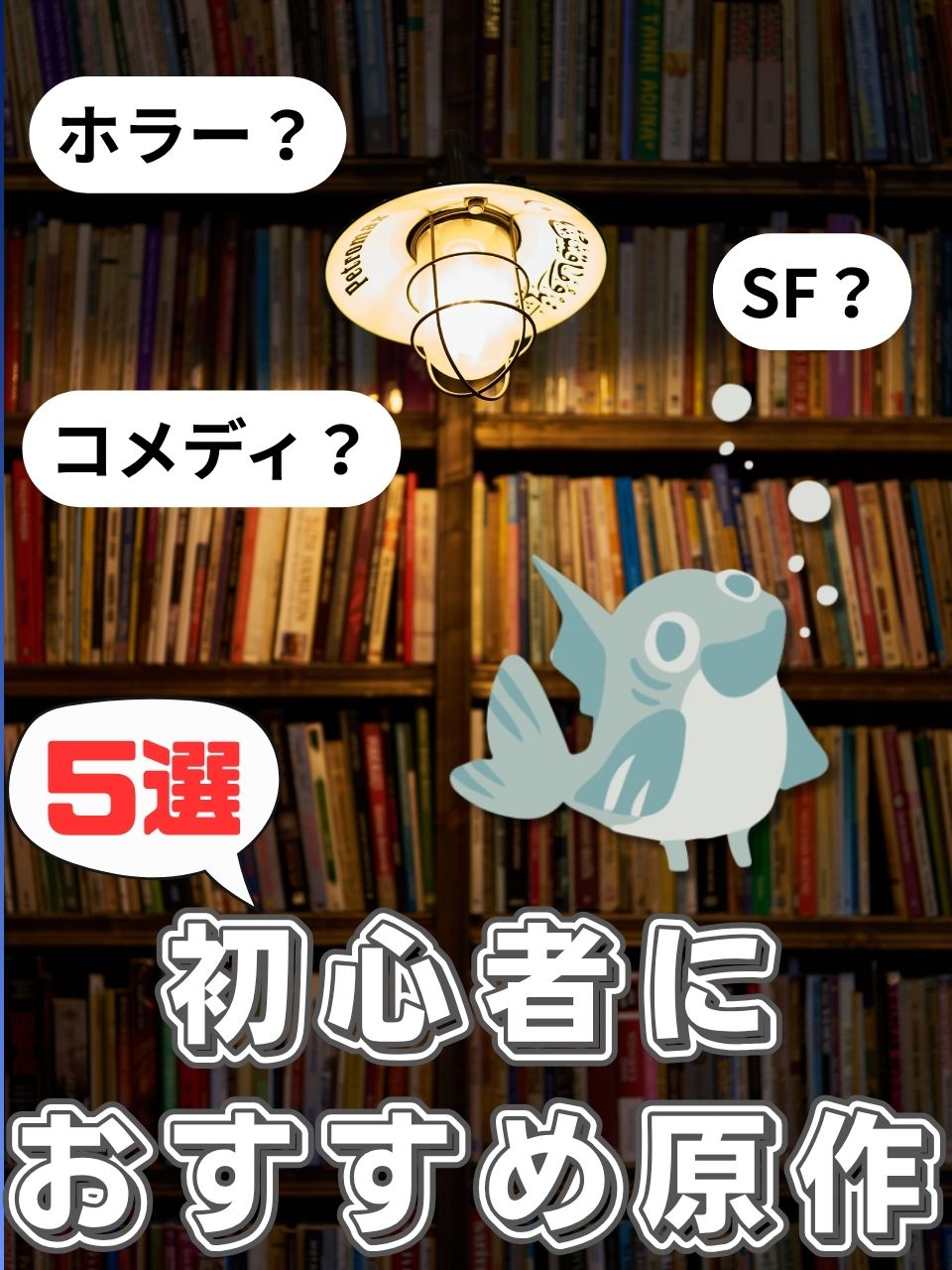
【初心者向け】「どれから読めばいい?」クトゥルフ神話初心者におすすめの原作5選
目次
前置き
クトゥルフ神話に興味はあるけど、「どの作品から読めばいいか分からない」「難しそう」「怖すぎるのは苦手」—そんな風に思っていませんか?
確かにクトゥルフ神話は、独特の世界観や古典的な文体、馴染みのない固有名詞など、初心者にとってハードルが高く感じられるかもしれません。
でも安心してください!
クトゥルフ神話は決して「怖いだけ」の作品群ではありません。人間ドラマあり、コメディあり、心理サスペンスありと、実はとても多彩なジャンルなのです。
この記事では、初心者でも読みやすく、かつ面白いクトゥルフ神話の原作を5つ厳選しました。
選定基準は以下の通りです:
- 読みやすさ:文体や構成が親しみやすい
- 面白さ:ストーリーとして純粋に楽しめる
- 多様性:ホラー、ドラマ、コメディなど様々なタイプ
- 入手しやすさ:現在も読める翻訳版がある
- 神話体系での重要性:読んでおくと他作品も楽しめる
今回取り上げる5作品は、それぞれ異なるアプローチで神話を取り入れていますっ:
- インスマスを覆う影:スリル満点の脱出劇×クトゥルフ神話の代表作型
- 七つの呪い:童話風ブラックコメディ×邪神パレード型
- 緑の深淵の落とし子:泣ける人間ドラマ×美しき人外との悲恋型
- クラウチ・エンドの怪:スティーヴン・キング×異空間ホラー型
- シャフト・ナンバー247:SFサスペンス×考察必須の謎解き型
各作品について、以下の3点を詳しく解説しています:
- 基本情報:作品概要とあらすじ
- こんな人におすすめ!:ハッシュタグの形
- 読みどころ:魅力的なキャラクター・ストーリーを紹介
5作品はそれぞれ異なる魅力を持っているので、きっとあなたの好みに合う作品が見つかるはずです。気になった作品から、気軽に手に取ってみてください!
本編
1.「インスマスを覆う影」
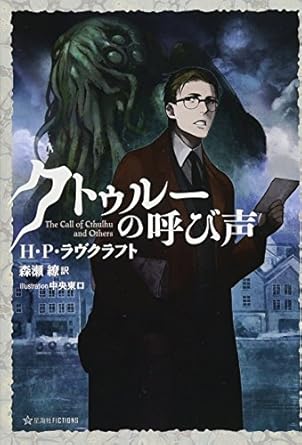
基本情報
- 作者名:ハワード・フィリップス・ラヴクラフト
- 執筆年/日本での出版情報:1931年/「クトゥルー8」・「新訳クトゥルー神話コレクション1」・「ラヴクラフト全集1」
- 読了時間の目安:1時間程度
- 作風:ホラー
あらすじ(ネタバレなし)
1927年の冬、マサチューセッツ州の港町インスマスが政府の秘密作戦により爆破され、地図上から消えた。
時は遡り、その年の夏。成人祝いの一人旅をしていたロバート・オルムステッドは、目的地への汽車が取れず、やむを得ずインスマスを経由するバスに乗ることになる。
かつて栄えたこの港町は、今や周辺住民から忌み嫌われていた。流行病で住民の半数以上を失って以来、町には呪いがかかっているという噂が絶えない。さらに不気味なことに、町の住民たちは奇妙な容貌をしていた—手足は異様に大きいのに耳や鼻は未発達で、その姿は人というより魚や蛙を思わせた。
町の異様な雰囲気に好奇心と不安を抱きながらバスに戻ったロバート。しかしバスが故障し、彼はこの不気味な町で一夜を明かすことを余儀なくされる。
果たしてロバートは、無事に朝を迎えることができるのだろうか…。
こんな人におすすめ!
#クトゥルフ神話の代表作から入りたい
#ハラハラするホラー展開が好き
#見つかったら終わりの緊張感を味わいたい
#生理的に怖い怪物が登場する作品が読みたい
#結末がすっきりする話が好き
#TRPG「インスマス」シナリオの元ネタを知りたい
#「深きもの」について詳しく知りたい
#他のクトゥルフ作品でよく言及される重要作品を読みたい
#漫画や映画でも展開されている人気作に触れたい

読みどころ・魅力
【物語の魅力】
政府がインスマスを検挙し、爆破したという「結果」から始まる物語なので、オチがわかっている分読みやすく、逆に「ここからどうやってあのオチになるのだろう」という期待感がうまく働いています!
最初から最後まで不穏な雰囲気がずっと続いていて、じめじめとしたホラーが好きな人には刺さると思います。
特に、町を探索するシーンから逃走劇まで、見つかったら命がないというスリルが持続します。
現在は森瀬先生の「新訳クトゥルーシリーズ」に収録されているので、比較的文体は読みやすくなっています。ただし、他の短編集で読む場合は少し古典的な文体で回りくどく感じるかもしれません。
【キャラクターの魅力】
登場人物は多いですが、中でも覚えておきたいのは、インスマスを深きものに売った元凶オーベット・マーシュと、真実を知る生き残りの人間ザドック・アレンの二人です。
主人公ロバートは外部からインスマスに来たよそ者で、基本的に町全体が「全員敵」という絶望的な状況に置かれてます。
そんな中で唯一の癒しは「売店の青年」です!
物語には影響しない脇役と言えば脇役…。
彼も別の街から派遣された人間で、インスマスの住人は警察の介入を避けたいため彼には手が出せません。登場回数こそ少ないですが、「絶対に死なない味方」という安心感を与えてくれる存在でしたっ。
【初心者に優しいポイント】
有名な作品が新訳に収録されているので、今から読み始める人にもおすすめ!
後のクトゥルフ神話作品に関わってくる重要な作品なので、本作を読んでおかないとインスマス関連の話が分からない可能性があります。
特に「深きもの」「オーベット・マーシュ」などは、他の作品でも頻繁に言及されます。
深きものの話は広げやすいためか、本作が刺さればインスマスをテーマにした作品を次々と掘り下げていくこともできます!
クトゥルフ神話TRPGでも「インスマス」は定番シナリオの一つです。
【メディアミックス】
田辺剛先生による漫画化と、日本で制作された映画があります!
活字が苦手…という人は、まずこちらから入るのもおすすめです。特に漫画版は視覚的に深きものの不気味さが伝わりやすく、原作理解の助けになります。






正直、本作を通らずにクトゥルフ神話を理解していくのは、無理なのではないというくらいに、他の作品でもこすられてます!
もっと詳しく知りたい人はコチラ!
2.「七つの呪い」
あらすじ(ネタバレなし)
コモリオムの行政長官、ラリバール・ヴーズ卿。彼の日常は、思いもよらぬ形で崩壊する。
蛮族ヴーアミ狩りの最中、妖術師エズダゴルの儀式に遭遇してしまったヴーズ。怒り狂った妖術師は、彼に恐ろしい呪いをかけた—邪神ツァトゥグァへの生贄として捧げられるという運命を。
怪鳥ラフトンティスに導かれ、ヴーズはヴーアミタドレス山の地下洞窟へと追いやられていく。強力な呪いに操られ、ツァトゥグァの御前に立つが、皮肉にも神は満腹だった。ツァトゥグァは新たな呪いを加え、ヴーズを次の神への貢物とする。
ここから、ヴーズの悪夢のような旅が始まる。蜘蛛神アトラク=ナチャ、妖術師ハオン=ドル、蛇人間、アルケタイプ、アブホース…。誰も彼を受け取ろうとはせず、次々と新たな呪いを加えられながら、様々な存在の間をたらい回しにされる。
七つの呪いを受けたヴーズの運命は、果たしてどこへ辿り着くのか―。
こんなシナリオにおすすめ!
#ホラーが苦手だけどクトゥルフ神話に興味がある
#童話や絵本のような雰囲気が好き
#ブラックユーモアや不条理コメディが好き
#サクサク読める短編を探している
#複数の邪神をまとめて知りたい
#ツァトゥグアやアトラク=ナチャに興味がある
#邪神との会話シーンを読んでみたい
#怖いだけじゃない、ちょっと可愛い神話作品を読みたい
#クラーク・アシュトン・スミスの作品に触れたい






読みどころ・魅力
【物語の魅力】
妖術師の儀式を邪魔してしまったヴーズは、最初の呪いをかけられます。そこからタイトル通り、計7つの呪いをかけられることになります。
本来なら邪神の生贄になるというのは事実上の死刑宣告で、体の自由を奪われたまま邪神の元へ向かうのは絶望感しかないはずです。読み始めた時はそういうホラーなのかと思ったのですが、最初にツァトゥグアの前に立った時「満腹だから食べない」と言われ、この時点で本作がホラーではないことがわかりました!
それから蜘蛛神アトラク=ナチャやアブホース、神話生物の蛇人間の元にも次々と送られていきます。しかしタイトルの通り7つの呪いをかけられることが分かっているので、逆に言うと「ここで死ぬことはない」という安心感を持って読めます。
物語の構造が面白いのもポイントです。 各邪神とのやり取りは短くテンポよく進むため、飽きることなくサクサク読み進められます。「次はどんな邪神が登場するのか」「今度はどんな理由で断られるのか」という期待感で、ページをめくる手が止まりませんっ。
文体も親しみやすく、 クラーク・アシュトン・スミス特有の幻想的で装飾的な表現が、おとぎ話のような雰囲気を作り出しています。暗く重苦しいラヴクラフト作品とは対照的な、軽やかな読み心地が魅力です。
【キャラクターの魅力】
主人公ヴーズは決して純粋な善人ではありません。行政長官という権力者で、蛮族狩りをしていたところを妖術師に見られたわけですから。しかし呪いをかけられ、次々とたらい回しにされる様子は、どこか同情を誘います。
本作最大の魅力は、邪神たちの描かれ方です。 本来、邪神と聞くと見ただけで「死」を連想させるほど凶悪な存在のはず。しかし本作は違います。全員が「邪」とは思えないほど、慈悲に溢れ、むしろ可愛く描かれています!
ツァトゥグアは満腹だからと断り、アトラク=ナチャは橋の建設に忙しいからと次へ送る。それぞれの邪神が明確な「個性」を持ち、まるで人間のように理由を述べて断るのです。この擬人化された邪神たちの姿は、クトゥルフ神話の新しい一面を見せてくれます。
特に印象的なのが、邪神たちの会話シーンです。 通常のクトゥルフ神話では、邪神は人間とコミュニケーションを取らない恐ろしい存在として描かれます。しかし本作では、邪神たちがヴーズと(一方的ですが)会話し、それぞれの理由で彼を受け取らない様子が描かれます。
こうした「たらい回し」の連鎖が、物語にリズムと笑いをもたらしています!
【初心者に優しいポイント】
従来のラヴクラフト調のクトゥルフ神話は、どこか読みにくく、姿を見せない恐怖が特徴でした。古典的な文体、難解な固有名詞、はっきりしない描写…初心者にはハードルが高い要素が多かった印象です。
しかし本作は絵本や童話のような展開で、次の展開が予想できる安心感があります。「7つの呪いがかけられる」という構造が最初から分かっているため、物語の流れを把握しながら読み進められます。
特に「ホラーが苦手だけどクトゥルフ神話に興味がある」という人に最適です!
クトゥルフ神話のイメージとして、「ホラーが苦手で興味はあるけど読めない…」という意見をよく聞きますが、本作はその点でも問題ありません。
むしろ邪神たちがこのくらい緩い存在なのではないかと錯覚してしまうほどです。本作から始めると他の作品との温度差にやられる可能性はありますが、「怖くない」という点で、間違いなく初心者におすすめできます。
短編なので読了時間も短く、 通勤・通学の合間や寝る前の30分程度でサクッと読めてしまうのも嬉しいポイント。「クトゥルフ神話を1作品読んでみたい」という最初の一歩に最適な作品です。
また、ツァトゥグア、アトラク=ナクア、アブホースといった複数の邪神を一度に知れるため、神話生物図鑑としても機能します。 TRPGでこれらの邪神を扱う際の参考にもなるでしょう。






クラーク・アシュトン・スミスはある意味で一番邪神の扱い方が上手だと思います。
本作ほどじゃなくても、彼の作品は大体神話生物が可愛いです。
もっと詳しく知りたい人はコチラ!
3.「緑の深淵の落とし子」
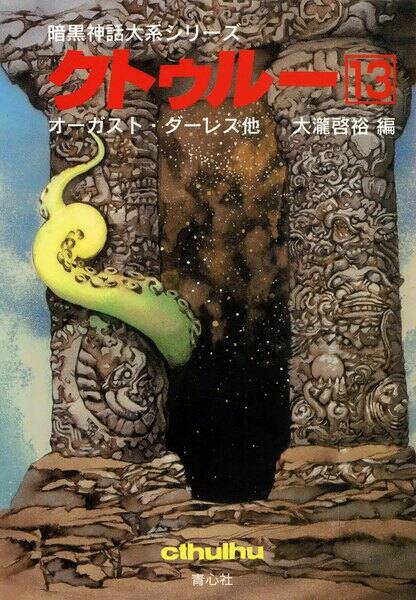
基本情報
- 作者名:カール・ホール・トンプソン
- 執筆年/日本での出版情報:1946年/「クトゥルー13」・「真ク・リトル・リトル神話体系4」
- ページ数・読了時間の目安:1時間程度
- 作風:ホラー/人間ドラマ
あらすじ(ネタバレなし)
死刑判決の日、法廷に立つジェームズ・アークライト医師。妻と胎児の命を奪った罪で、彼は死を宣告される。奇妙なことに、ジェームズはその判決を望んでいた。
脳神経外科医として激務に追われていた彼は、指の震えを抑えるため、人口わずか50人ほどの小さな町ケールスマスを訪れる。閉鎖的でよそ者に厳しい町だったが、その静けさこそ彼が求めていたものだった。
町で同業のエブ・リンダー医師と親しくなったジェームズは、ある日、他の家々とは異質な雰囲気を持つ館を発見する。その館に住むラザルス・ヒースは元船乗りで、謎めいた娘カッサンドラと二人暮らし。町の人々は「知らないほうがいい」と口を閉ざすが、ジェームズはその警告を無視してしまう。
ある日突如として現れたカッサンドラ。この出会いが、彼の人生を取り返しのつかない闇へと引きずり込んでいく―。
こんなシナリオにおすすめ!
#人間ドラマ重視のクトゥルフ神話を読みたい
#泣けるホラーを探している
#恐怖よりも切なさや感動を求めている
#主人公に同情できる物語が好き
#悲劇的な恋愛要素のある作品が読みたい
#ホラーが苦手だけど深い物語に触れたい
#「深きもの」とは違う美しい魚の神話生物に会いたい
#しっとりとした雰囲気の作品を求めている






読みどころ・魅力
【物語の魅力】
妻とそのお腹の子供を射殺した罪で、死刑判決を受ける主人公アークライト。物語は、この衝撃的な結末が分かった状態から始まります。
一見すると狂った主人公に見えますが、実際はこうなるまでに切ない出来事があったのです。読者は「なぜ愛する妻を殺さなければならなかったのか」という謎を抱えたまま、過去へと遡っていきます。
舞台となるのは、閉鎖的な田舎町ケールスマス。 そこには住人から後ろ指を指される親子がいました。父親ラザルス・ヒースには異様な生臭さがあり、鱗と首元のエラを持ち、明らかに人間から逸脱している。そして娘カッサンドラ—見た目こそ美しいものの、その生い立ちは不明瞭で、母親がいない謎の存在です。
こうした狭い環境に漂う神秘的な雰囲気が本作の魅力です。田舎町特有の閉塞感と、秘密を抱えた人々の不穏な空気感が、物語全体を包み込んでいます。
アークライトもカッサンドラが普通の人間ではないことを察していたはずです。それでも彼は本気でカッサンドラを愛していました。一方でカッサンドラは真実を知っています。自分の母親が何者なのか、自分は「人間」という生き方をしてはいけないこと、「人間」と同じ幸せは体験できないこと。
でもアークライトと出会い、彼に恋をしてしまう。 この禁じられた恋が、物語の核心です。
クトゥルフ神話版の「人魚姫」と言っても過言ではない作品で、人外との悲恋が美しく描かれています。しかしこの恋愛の最期は「射殺」というのも冒頭で分かっているため、これがまた辛い…。ハッピーエンドではないと分かっていながらも、応援したくなる二人の関係がとても良かったです!
物語の構造も巧みですっ。 冒頭で結末を提示することで、読者は「どうしてこうなったのか」という疑問を持ちながら読み進めます。過去へと遡るたびに、真実が少しずつ明かされ、最後には全てが繋がる瞬間が訪れます。この構成が、物語に深い余韻を残しました。
ただし、「恋愛モノ」として本作を読むのは危険です。ちゃんとクトゥルフ神話らしいホラー作品なので、泣ける人間ドラマとしてのホラーが好きな人におすすめします!
【キャラクターの魅力】
本作の最大の魅力は、一途な男アークライトと、人外の娘カッサンドラの「純愛」です。
アークライトは誠実で真面目な医師として描かれます。 激務に追われ、指の震えという職業的危機に直面していた彼が、静かな町で出会ったのがカッサンドラでした。彼女の異質さを感じ取りながらも、その美しさと神秘性に惹かれていく様子は、理性と感情の葛藤として丁寧に描かれていますっ。
一方カッサンドラは、悲劇のヒロインそのものです。 彼女は自分が「何者」であるかを知っており、人間として生きることが許されないことも理解している。それでもアークライトへの愛を抑えられない。この切なさが、読者の心を強く揺さぶります。
ハリウッド映画ばりに感情が揺さぶられる描写があり、活字からでもキャラクターの表情まで容易に想像できるほど、表現豊かなやり取りが続きます。特に二人が心を通わせる場面は、美しくも切ない…。
さらに注目すべきは、アークライトの妻の描写です。 彼女は狂っていく過程が切なく、邪神の力には抗えないという絶望感を体現しています。
登場人物全員が被害者であり、誰も悪くない。 ただ運命が残酷だっただけ—この構造が、物語を一層悲劇的にしています。
【初心者に優しいポイント】
クトゥルフ神話の分かりやすい「邪神ドーン!死体ドーン!」みたいなゴア描写が苦手な人でも読めるくらい、落ち着いた雰囲気の作品です。
本作ほど恋愛に重きを置いた人間ドラマな作品は、クトゥルフ神話の中でも稀です。 TRPGで「エモシ」と言われるシナリオが好きな人には、がっつり刺さると思います!
感情移入しやすく、キャラクターの心情に寄り添いながら読み進められるため、物語への没入感が非常に高いです。
また、恋愛に重きを置いているとはいえ、ちゃんとクトゥルフ神話作品です。邪神ヨス=カラは姿を見せますし、ホラーな展開もしっかりあります。なので物足りないということは絶対にありませんっ。
特に「深きもの」との比較が興味深いポイントです。 『インスマスを覆う影』に登場する深きものは、生理的嫌悪感を催す魚顔の怪物として描かれます。しかし本作のカッサンドラは、鱗やエラこそあるものの、人魚姫のような幻想的な美しさを持っています。同じ「人間と神話生物の混血」でも、こうも印象が違うのかという発見があります。
文体もしっとりとしていて読みやすく、 ラムジー・キャンベルの筆致は現代的で親しみやすいです。ラヴクラフトの古典的な文体が苦手な人でも、すんなり読み進められるはず。
心理描写が丁寧なので、ホラー初心者でも安心して読めます。 急に怖いシーンが来るというよりは、じわじわと不穏さが増していく構成なので、心の準備をしながら読めるのも嬉しいポイントです。
「クトゥルフ神話=ただ怖いだけ」という先入観を覆し、人間ドラマとしても一級品の作品があることを知ってほしいです!






ドラマも映画も存在しないのに、なぜかこんな話見たことがあるような気がするという親近感も良かったです。
もっと詳しく知りたい人はコチラ!
4.「クラウチ・エンドの怪」
あらすじ(ネタバレなし)
ロンドン郊外のクラウチ・エンド。静かな夜の派出所で、新任のファーナム巡査と長年この地区を担当するヴェター巡査が会話を交わしていた。
先ほど派出所を訪れたアメリカ人女性ドリス・フリーマンは、取り乱した様子で「ロニーを探してちょうだい」と訴えていた。ファーナム巡査はこれを「狂言」と切り捨てようとするが、ヴェター巡査は冷ややかな微笑を浮かべるだけだった。
「世界をひとつのボールだと考えてみろ。どこもかしこも均一な厚さではない。皮の薄くなっている部分があるんだ—それがクラウチ・エンドだ」
ヴェターが取り出した特別なファイルには、通常の事件報告とは一線を画す奇妙な記録が残されていた。
旅行でロンドンを訪れていたフリーマン夫婦は、友人を訪ねるためクラウチ・エンドへ向かった。しかしタクシーは次々と乗車を断り、電話ボックスでロニーが住所を調べている間に、乗ってきたタクシーは忽然と姿を消した。
午後6時から、ドリスがひとり派出所に辿り着く午後10時15分まで—その4時間に、いったい何が起きたのか。
クラウチ・エンド。この世界と別の何かとの境界が薄くなる場所で、ロニーはどこへ消えたのか―。
こんなシナリオにおすすめ!
#スティーヴン・キングの作品が好き
#現代的な文体のクトゥルフ神話を読みたい
#異世界に迷い込むような話が好き
#警察視点の物語に興味がある
#心理ホラー要素のある作品を求めている
#額縁構造(話の中の話)の物語が好き
#じわじわと不安が高まる雰囲気を楽しみたい
#名前のない神話生物に興味がある
#映像化された人気作品を読みたい






読みどころ・魅力
【物語の魅力】
妻のドリスは助かっているが、夫のロニーは行方不明—この結末が分かった状態で物語は始まります。
しかもフリーマン夫婦が体験したのは、昼から夜までのたった4時間の出来事。この短時間に何が起きたのか、という謎が読者を引き込みます!
クラウチ・エンドという場所は、地元の人からしても「曰くつき」の場所です。 新人のファーナム巡査は懐疑的ですが、長年勤めているヴェター巡査はこの町が異常であることを知っている。この警察内部の温度差が、物語にリアリティと不穏さを与えています。ホラー映画では警察が無能に描かれがちですが、本作の警察は事態を理解している—この設定が新鮮で、説得力があります。
物語は違和感が積み重なっていきます。 最初の違和感は、顔も知らない会ったこともない友人に、わざわざクラウチ・エンドまで会いに行くという動機。
事件に巻き込まれるまでの動機って、本当に何でもいいんだと逆に納得してしまいました。
次の違和感は「看板の文字」です。「60人の人間が行方不明、死亡ではなく、あえて遭難という言葉を使っている」と、妻ドリスも違和感を覚えていました。地下鉄事故なら「死亡」や「衝突」を使うはずなのに、なぜ「遭難」なのか。 この言葉選びの不自然さが、クラウチ・エンドが「普通の場所ではない」ことを暗示していますっ。
読者もこの町で夫婦が同じように「遭難」するんだろうなという心構えができる分、展開が予想しやすく読みやすい作品です。
また、スティーヴン・キングと聞くと、「IT」「キャリー」「シャイニング」など、「人間が怖い」作品のイメージがあるかもしれません。 しかし本作は上記の作品と異なり、ちゃんと異形の怪物が登場するホラーです!
本作は「不思議の国のアリス」に近い構造を持っています。 夫婦が不思議の国「クラウチ・エンド」に迷い込み、異形たちと遭遇しながら元の世界に帰ろうとする。この「異世界迷い込み型」の展開は、クトゥルフ神話の中でも珍しいです。
さらに本作独自の魅力として、「現実の皮が薄い」という例え話があります。 ヴェター巡査が語る「世界はボールのように均一ではなく、薄くなっている部分がある」という説明は、クトゥルフ神話の世界観を非常にわかりやすく表現しています!
【キャラクターの魅力】
現代の作家なだけあって、夫婦のやり取りが映画のようで、すごくとっつきやすいです。感情移入しやすい、どこにでもいるような夫婦というのも良い点でした。旅行中の些細な会話や、道に迷った時の反応など、リアルな夫婦の姿が描かれています!
ドリスの視点で語られるため、彼女の恐怖や混乱が読者にダイレクトに伝わりますっ。夫ロニーが徐々に変わっていく様子、町の住人が人間に見える瞬間と人外に見える瞬間があり、「町が異常なのか、自分たちが狂っているのか」という不安。この曖昧さが心理ホラーとしての魅力を高めていますっ。
そして異形側ですが、個人的に一番印象深いのは、タクシーでクラウチ・エンドに着いたときに遭遇した片目の猫です。
ただ不穏な雰囲気を出すだけの役割かと思いきや、この猫もしっかりと異世界の異形サイドに属しています。ネタバレは避けますが、「不思議の国のアリス」に登場する「チェシャ猫」のような印象を受けました。この猫の存在が、物語全体に童話的な不気味さを加えている気がします!
他にも名前のない神話生物が何体か登場します。既存の有名な邪神ではなく、キング独自の創造物が登場するため、「知らない怪物との遭遇」という新鮮な恐怖を味わえます。
ヴェター巡査とファーナム巡査の対比も見事です。 経験豊富なヴェターの落ち着きと、懐疑的な新人ファーナムの反応。この二人の会話を通じて、クラウチ・エンドの異常性が徐々に明かされていく構成が面白いです。
【初心者に優しいポイント】
まず、共通して「怖すぎない」というのを念頭に置いています。ただし怖くないクトゥルフ神話作品も数多く存在する中で、ちゃんと他とは違う魅力があるかで見た時、本作は一番「現代」の作品なのです。
スティーヴン・キングはまだ存命で活躍されている方で、ホラー界隈では知らない人はいないくらいの知名度です。ホラーが苦手な人でもキングの作品なら、もしかしたら見たことがある、見たことはないけど知っている、興味がある、という方もいるのではないでしょうか。
クトゥルフ神話のハードルの高さは「読みにくさ」や「知らない作家ばかりでどこから手をつけたらいいかわからない」といった点だと思います。そういう点で、本作は知っている作家という安心感と、読みやすさでおすすめしたい一作となっています!
文体も現代的で親しみやすく、ラヴクラフトの古典的で装飾的な文章とは対照的です。会話文が多く、場面転換もスムーズで、映像が頭に浮かびやすい書き方をしています。キングの得意とする「普通の人々が異常事態に巻き込まれる」という構造も、読者が感情移入しやすい要因です。
また、短編なので読了時間も短く、1時間程度でサクッと読めてしまうのも嬉しいポイント。「クトゥルフ神話を1作品読んでみたい」という最初の一歩に最適です!
「額縁構造」という物語形式も、初心者に優しい要素です。警察署でヴェターがファーナムに話を聞かせるという形式なので、読者は「安全な場所」から恐怖を眺めることができます。ドリスの体験談という形で語られるため、過去の出来事として距離を保ちながら読めるのです。
キングからクトゥルフ神話に入るという逆ルートも魅力的です。通常はラヴクラフトから始めることが多いですが、キングのファンなら「キングが書いたクトゥルフ神話」という切り口で興味を持てるでしょう。
【メディアミックス】
本作は映像化されていて、「スティーブン・キング短編シリーズ 8つの悪夢(ナイトメアズ)I」に収録されています。
原作からほぼ改変されていないので、活字が苦手な人は映像作品から入っても同じ面白さを体験できます。ただし映像で見ると、異形の姿がよりはっきりと描かれるため、原作のぼんやりとした恐怖とは少し印象が異なるかもしれません。
逆に、映像作品を先に見てから原作を読むのもおすすめです。場面が想像しやすくなり、より深く物語を楽しめるでしょう!






キングの作品は言わずもがなの名作揃いなので、悩んだら本作から読んでみてもいいかもっ。
5.「シャフト・ナンバー247」
あらすじ(ネタバレなし)
深夜の監視室。青白いモニターの光が、ドリスコルの無表情な顔を照らしていた。彼はこの仕事が好きだった—複雑な配管網と数百のシャフトが作り出す迷宮のような施設の、静寂と孤独を。
しかし同僚のウェインライトは違った。彼は常に神経を尖らせ、些細な警報音にも過剰に反応していた。その異常な反応は、2年前に起きたディームズの「事件」と関係があるようだった。
ドリスコルは上司ホートから「口外無用」と告げられ、資料室で調べようとするが、ディームズの日誌は全て閲覧禁止になっていた。謎は深まるばかり。彼はウェインライトに直接会うことにした。
「ディームズはシャフトの中にいる」—ドリスコルの言葉に、ウェインライトの顔から血の気が引いた。
ウェインライトが語るのは、シャフト・ナンバー247での異常な出来事。水漏れだけではない。奇妙な音、何かが動き回る影。そして「除去」されたシャフト247。
ディームズは「自由になりたい」と言っていた。そしてシャフトの向こう側に何があるのかを知ってしまった—。
彼らが毎日監視しているもの。そして彼らを監視しているかもしれないもの。
こんなシナリオにおすすめ!
#静かな恐怖を味わいたい
#不穏な雰囲気だけで進む物語が好き
#考察要素のある作品を求めている
#隠れた名作を発掘したい
#じわじわと謎が深まる展開が好き
#SFホラー的な設定に興味がある
#派手な展開がなくても楽しめる
#読後に余韻が残る作品を探している
#オチで世界観がひっくり返る体験をしたい






読みどころ・魅力
【物語の魅力】
「シャフトをただ観察するだけ」の仕事。この時点でもう意味が分かりませんが、なんと、この観察の目的が最後まで明かされないから面白い!本当に何の仕事なのか分からない…という不安が読者を包みます。
そもそもディームズは仕事中に「何か」を目撃してしまったわけで、となると「この仕事の意味ってつまり…」と察してしまうけれど、確信は持てない。この曖昧さが不穏さを増幅させます。
こういう風に頭の中で推理しながら読んでいくと、読み終わった時には真の面白さに出会えるはずです!
本作最大の特徴は、「何も起きない恐怖」です。派手な展開もなく、怪物が襲ってくるわけでもない。ただ不穏な空気が漂い続け、謎が深まっていくだけ。しかしこの「静けさ」こそが、じわじわと心を侵食する恐怖を生み出しています。
物語は三層構造になっています。まず表層にあるのは、ウェインライトの異常な行動。その下にはディームズの失踪事件。そして最も深い層には、シャフト・ナンバー247の秘密がある。読者はドリスコルと共に、一層ずつ真実に近づいていきます。
「247」という数字の意味も、考察のしがいがあります。なぜこの番号なのか。タイトルに冠されるほど重要な数字には、必ず意味があるはず—読後に考えを巡らせる楽しみがあります。
短編ながらにして完成度が高く、TRPGが好きでクトゥルフ神話に興味を持ったという人にはおすすめです。特に「閉鎖空間」「監視」「秘密」といった要素は、TRPGのシナリオ作りにも応用できる設定です。
【キャラクターの魅力】
主人公はドリスコルですが、彼はディームズの事件も一緒に働くウェインライトのことも、基本的には懐疑的で「頭のおかしいやつ」としか考えていません。
この性格こそ読者と同じだと思います。何も分からない、何も教えてくれない。そんな中で神経を尖らせて「監視」の仕事をこなしている人がいたら、少し引いてしまうのも分かります。読者はドリスコルの視点を通じて、徐々に真実に気づいていくのです。
ただし、ドリスコルの魅力は感情移入のしやすさだけではありません!彼はこう見えてすごく仲間思いなのです。
クール系に見えて実は優しいというギャップ。ただ優しいだけのキャラと違って、なぜかより「良い人」に見えてしまいます。ウェインライトの異常な行動を心配し、上司に相談し、資料を調べ、直接会いに行く—この行動力と思いやりが、ドリスコルを魅力的な主人公にしています。
ウェインライトの描写も秀逸です。彼は単なる「怖がりの同僚」ではありません。親友ディームズを失った悲しみと、真実を知ってしまった恐怖を抱えながら、それでも仕事を続けている。彼の震える声、血の気が引く顔—これらの描写が、読者に「何かがおかしい」と確信させます。
そして姿を見せないディームズ。彼は物語に直接登場しませんが、その不在こそが物語の核心です。「自由になりたい」と言っていたディームズは、果たして何を見つけたのか。彼の存在が、物語全体に影を落としています。
さらに注目すべきは、「監視する側」と「監視される側」の曖昧さです。彼らはシャフトを監視していますが、もしかしたら彼ら自身が監視されているのかもしれない—この不安が、キャラクターたちの緊張感を高めています。
【初心者に優しいポイント】
短編なので展開が早いのもそうですが、本作は疑問から真実に至るまでの段階が綺麗で、すんなり読めるのが特徴的です!ドリスコルの認識が少しずつ変わっていく様子も丁寧に描かれています。
読み始めは絶対にもやもやすると思います。むしろ不親切な作品だと悪く捉えてしまうかもしれません。「何も説明してくれない」「状況が分からない」—この不満は、当然でしょうっ。
しかしそれを覆すように、少しずつ確実に真実に近づいていくので、クトゥルフ神話作品×謎解きのような感覚で読めます。好きな人にはずっぷりと刺さる作品だと思います。
ただし、本作は5選の中で最も「上級者向け」です。他の4作品とは異なり、明確な答えを提示しません。読者自身が考え、解釈する余地を残しています。そのため、他の4作を読んでからステップアップとして挑戦するのがおすすめです。
また、本作はこれで完結していますが、後日談のような続編もあります!
個人的にはこれも面白いから続編が出たのではないかなと思ってしまいます。
本作の魅力は「余白の美学」です。全てを説明しないからこそ、読者の想像力が刺激されます。クトゥルフ神話の本質である「知ってはいけないことを知る恐怖」が、この作品では完璧に表現されています。






明確なホラーな場面はないです。なのに「ホラー」だと思わせる描写が巧みすぎて、クトゥルフというより文学のような面白さがありました!
まとめ
いかがでしたか?クトゥルフ神話と聞くと「難解で怖い」というイメージがあるかもしれませんが、実際には様々な作風の作品が存在しますっ。
今回紹介した5作品を改めて振り返ってみましょう:
- 「インスマスを覆う影」:クトゥルフ神話の代表作。スリル満点の逃走劇と、すっきりする結末で初心者でも読みやすい作品です。
- 「七つの呪い」:ホラーが苦手な人でも安心。邪神たちのたらい回しという、ユニークで可愛らしい展開が魅力です。
- 「緑の深淵の落とし子」:人外との切ない恋愛を描いた、クトゥルフ神話版「人魚姫」。感動重視の方におすすめです。
- 「クラウチ・エンドの怪」:スティーヴン・キングが描く異世界迷い込み型ホラー。読みやすく、映像化もされている人気作です。
- 「シャフト・ナンバー247」:何も起きないのに怖い。考察要素たっぷりの上級者向け作品。他の4作を読んだ後のステップアップに最適です。
あなたにおすすめの読む順番は?
- クトゥルフ神話らしさを味わいたい ― 「インスマスを覆う影」
- ホラーが苦手 ― 「七つの呪い」
- 感動したい ― 「緑の深淵の落とし子」
- 現代的で読みやすい作品から ― 「クラウチ・エンドの怪」
- じっくり考察したい ― 「シャフト・ナンバー247」
もちろん、気になった作品から読んでいただいて構いません!
クトゥルフ神話の世界は広大で、今回紹介した5作品はほんの入り口に過ぎません。しかしこの5作品を読めば、クトゥルフ神話の多様性と魅力が十分に理解できるはずですっ。
そして気に入った作品があれば、同じ作家の他の作品や、同じテーマを扱った作品へと広げていくのも楽しいでしょう。
TRPGをプレイする際の理解も深まると、より面白くなるはずです!